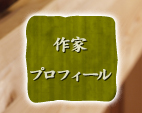筒井 修 (つつい おさむ)
筒井 修 (つつい おさむ)
1948年 長野県飯田市に生まれる
1976年 笠間市に築窯。作陶。
国内外にて個展を開催。
三角屋根のご自宅は作家ご自身が建てたとか・・・。敷地内には工房と小さなギャラリースペースがある。
春先に伺った時、ガサガサ落ち葉を踏む足元から草木の新芽を見つけ「オイオイ」と喜んでいらっしゃいました。
その光景は、器の表情と重なります。
 森田榮一(もりた えいいち)
森田榮一(もりた えいいち)
1948年 福岡県大牟田市に生まれる
1972年 明治大学卒業。
1988年 南吉原に移転。作陶。
国内外にて個展・グループ展開催。
「昔、見ていた風景が作品になっている」と作家は話されます。
昔、大牟田市は炭鉱の街。
「汗や油でギトギトした男達が沢山いたなぁ~」
そんな風景を一緒に見ている気持ちになります。
 G0JA WORKS (takako&masa)
G0JA WORKS (takako&masa)
ステンドグラスと陶器のコラボ作品。
「楽しいものをつくろう!」と2006年に結成。
硝子のTAKAKOさんは、お父さまの仕事の関係で海外生活の経験もあるらしく、どこかヨーロッパの家庭の灯りを連想します。
MASAさんが作ったやきものにTAKAKOさんがガラスを入れていく。二人の笑い声が聞こえるような作品。栃木弁でちょっと間が抜けた人のことを「ごじゃっぺ」と言うらしい。なるほどだからユニット名がGOJA Worksなのですね。
 佐藤健太・和美(さとうけんた・かずみ)
佐藤健太・和美(さとうけんた・かずみ)
健太 1959年 仙台市に生まれる
1982年 東京商船大学卒業後、広告関連に従事
1992年 陶芸を目指し、笠間市に移動
和美 1955年 鳥取市に生まれる
1982年 東京芸術大学デザイン科修士課程修了
1992年 笠間市で筒井修氏に師事
釉薬を使わない。土を塗り重ねて風合いを出している。
かなりの手間をかけていることを知った。
作家の生き方を感じる時間でもあります。見習いたい。
舘野文香(たてのあやか)
1987年 阿佐ヶ谷美術専門学校プロダクトデザイン科卒業
1993年 栃木県窯業指導所にて研修
1994年 筒井修氏に師事
1997年 メキシコ研修旅行 笠間にて独立
2010年 石岡市にて作陶
 坂野 晃平 (ばんのこうへい)
坂野 晃平 (ばんのこうへい)
1966年 愛知県常滑市に生まれる
1991年 愛知県立芸術大学大学院美術研究科彫刻専攻終了
中心軸を意識した球体の造形が多い。綺麗に整った球ではない。
鉄が錆びていく様な表情や割れは「振動」を感じます。
宇宙・生命・誕生・理・禅・・・そんなの全てが詰まっているらしい。
人が絶対的に大切にしなければならないことが、表現されているように思います。力でねじ伏せる事の限界。そこからは何も生まれない。それを知っていることが大切・・・・そんなお話しをしたこともありますね。
角田 武 (つのだたけし)
1959年 神奈川県横浜市に生まれる
1979年 岐阜県多治見市陶磁器意匠研究所終了
虎渓窯にて学ぶ
1984年 土岐市に築窯
粉引のトロリと柔らかな味わい。
灰釉の湯呑みは水の音が聞こえてきそうな涼しさがあります。
ミヤチヤスヨ 愛知県に生まれる。お花屋さんで働く。
常滑市で 独学にて作陶。木の実の器やハスの皿・枝カップなど森の中にいる様な器。
カランコロン音がするマラカス坊やには、命が吹き込まれ、人々を見守っている。
褒めてくれる。励ましてくれる。笑わせてくれる。考えるきっかけをくれる。時には叱ってくれる。側にいて欲しい存在です。
小川壮一(おがわそういち)
1971年 岡山に生まれる
1995年 筑波大学芸術専門学群総合造形コース卒業
1996年 陶芸家伊勢崎淳氏に弟子入り
2002年 独立 穴窯築窯
白備前や黒備前、岡山の赤土を使った作品など心にグッとくる。

松岡誠悟(まつおかせいご)
三本の登り窯を自ら手作りする。
ここまで綺麗に仕上がるのか・・・と観てしまう。器用さだけではない、「コツコツ丁寧に創り続ける」これも素晴らしい才能ですね。
細川敬 弘(ほそかわたかひろ)
1979年 岡山に生まれる
1999年 備前陶芸センター卒業
祖父竹村永楽の下で学ぶ
2000年 作陶
国内外にて個展・グループ展を開催。
素朴であること。素直であること。
昔懐かしい景色を思い出させてくれる。
きっと作家自身の中にある懐かしく心地よい風景なのでしょう。
光藤 佐((みつふじたすく)
天と地の間を生き物が悠々と行ったり来たりしている。それだけで一日頭の中で遊べる気がします。
器の美しさは、見た目だけではない。9年前に東京のギャラリーでお茶をいただいた時の感触が忘れられない。今も変わらない。
この感動が抑えきれず2年前に初めて作家に会いに行きました。「書」も素敵。「絵」も素敵。
田村浜男(たむらはまお)
1958年 群馬県に生まれる
1976年 日本工業大学建築科に学ぶ
1986年 岐阜県瑞浪市の里山に大窯を築き「彩火窯」とし、独立
1987年 独自の大窯を築く
1995年 草庵「山帰来」を設計、建てる
1997年 5室の登り窯を築く
2008年 穴窯を築く
瑞浪の自然豊かなところで土を掘り、砕き、手作りの窯で夫婦で
交替し窯の番をする。愛情に溢れている。
こういう作品を生活の中で使うことの意味を伝えたい。
古川欽彌・雅子(ふるかわきんや・まさこ)
古川欽彌 1965年 佐賀県に生まれる
1987年 東洋大学卒業
1991年 小野卓氏に師事
1994年 波多野善蔵氏に師事
1996年 坂田甚内氏に師事
1997年 八郷葦穂窯開窯
古川雅子 1969年 東京都に生まれる
1994年 武蔵野美術大学卒業
欽彌さんが成形し、雅子さんが絵付けをされるそうです。
国内外にて個展を開催されています。
河村穣(かわむらみのる)
加藤勢季子(かとうせきこ)
愛知県常滑市に生まれる
常滑高校デザイン科卒業
愛知県窯業職業訓練校(現窯業高等技術専門学校)卒業
河合塾学園トライデントデザイン専門学校非常勤講師
現在は、ご夫婦でこころや身体に健康問題のある子ども達に土に触れる楽しさを伝えている。
ドンドン・バンバン粘土を叩く子ども達。感触 を楽しんで入る「大丈夫だよ。粘土はやり返してこないからね」
を楽しんで入る「大丈夫だよ。粘土はやり返してこないからね」
加藤洋史(かとうようし)
富永琢磨(とみながたくま)
有城利博(ありしろとしひろ)
1974年 福井県に生まれる
東北大学文学部卒業後、新潟県で家具製作に従事。
2005年 伊豆に移住。NPO法人伊豆森林夢巧房研究所で
木工デザイナー・時松辰夫氏にて木の器づくりの
手ほどきを受ける
2011年 ありしろ道具店を設立
「自然に学び、木の道具をつくり、人と話し、地域をみつめる」
有城利博さんのブログより。人柄を感じます。
菊池奈美(きくちなみ)
必要とされなくなったものを生まれ変わらせてくれる。それを好いてくれる人に渡す。
作家が大切にしてることをお思い出しては忘れまた思い出す。
実践していることの意味は大きい。言葉に強さがある。幸福感を感じる。
大矢拓郎(おおやたくろう)
作品を大風呂敷に包んで、夜行バスでやってきた。
大学を途中で辞めて木工の仕事を考える。
我谷盆に出会い、佃眞吾氏の元で5年修行し独立。
デザインのもっと先にあるものを感じる。素朴で温かい。
人間が必要として作られた生活の道具であるが、人の手が入っている感がしない。
自然のあるがままを感じる作品です。
大矢さんから学ぶこと沢山あり、「素直で丁寧」。作品から作家の生き方感じます。
松本十糸子(まつもととしこ)
1999年 北鎌倉「織舎」佐藤京子氏の元で織を学ぶ
2007年 静岡市にて制作活動を始める
水野俊治(みずのとしはる)
1953年 愛知県常滑市に生まれる
1992年 愛知県窯業高等学校卒業
玉山窯 玉置保夫先生に師事
1993年~97年 同校講師
1997年 岐阜県八百津町に陶房「風姿」開窯
国内にて個展・グループ展を開催される
柔らかな曲線とふわっと優しい器の景色は、自然を尊ぶ心が溢 れている。ひっそりと作陶。作品は、使う人の気持ちをスーッと包んでくれる。